6月20日 井上ひさし「四十一番の少年」(文春文庫)を読む
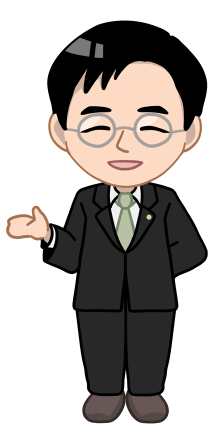
近くの書店で平積みにされていたのを買ってしまい、仕事の合間に読みました。
かつて児童養護施設に入所した経験がある作者の自伝的小説が三つ。
「あくる朝の蝉」の場面。
「わたし」が孤児院の生活がイヤになって、父方の祖母にしばらく置いてくれないかと手紙を出す。祖母からの「とにかく帰っておいで」の返信を受けて、弟と一緒に祖母の家に行き、一晩を過ごすという物語。夕飯の時の祖母とわたしとの会話の場面が何とも切ない。
祖母が「孤児院はいやなのかね?」と問うと、わたしが「あそこに居るしかないと思えばちっともいやところじゃないよ」「でも、他に行くあてが少しでもあったら一秒でも我慢できるようなところでもないんだ。」 結局は嫌なんだろと突っ込みを入れれば終わりなんだろうが、当時の事情や時代背景が、子どもたちにそういう遠慮しがちな婉曲的な表現をさせざるを得なかったのではないかと思うと、なんとも切なく聞こえてくるわけである。

